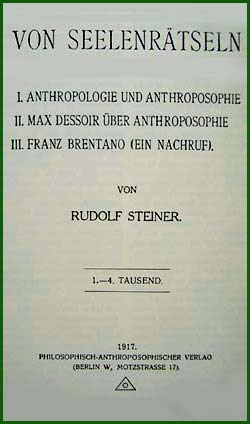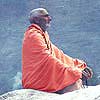|
■ |
人間の構成要素
人間の最も固有な本質は、神的なものから取り出されてきているために、人間は自分の内部に神的なものを見出す事が出来るのである。人間は神的なものを通して人間の第三の魂の構成を獲得する。
これは、アストラル体を通して外界についての知覚を受け取るように、神的なものをとおして自分自身についての内的な知覚を獲得するのである。 神秘学ではこの第三の魂の構成部分を「意識魂」と呼ぶこともできる。
神秘学的には、体的なものが三つの構成部分・「物質体」「エーテル体」「アストラル体」から成り立っているように、魂的なものは、三つの構成部分・「感覚魂」「悟性魂」「意識魂」からなりたつ。・・・・・・
・・・・・・・人間の七つの構成要素は「物質体」「エーテル体または生命体」「アストラル体」「自我」「霊我」「生命霊」「霊人」であり、これは 光の七色や音階の七音についてと同様であり、「光は(赤」)と(紫)の向こう側に眼が知覚出来ないだけだが色がまだアル」という反論には、物質体の向こう側にも霊人の向こう側にも人間の本質は継続していて、この継続が≪霊的に不可視≫であるにすぎない。
≪参考≫
アストラル体とは?
シュタイナーは、人間の内部では、親密にアストラル体は”知覚に持続性を与えている魂の部分”と結びつき、それを総合してアストラル体と呼び、厳密に言うならば人間のアストラル体を魂体と呼べると述べ、魂が魂体と一つになっている限り、魂を感覚魂ということもできる。と述べているが、分かり辛いので一般的な解釈で説明致します。
ジャーナリストの「立花隆」氏が「超常現象・臨死体験」等の調査研究過程で書いた書物にあった言葉です。『 アストラル体というのは、オカルトの世界では昔からある概念で、時代によって人によって、その使い方が違うので、簡単には定義できないが、一口で言うと、人間の構成要素として魂と肉体の間にある中間体的なものである。
非物質的な生命の担い手で、通常は肉体の内部に宿って、肉体と同じような形をしているが、形は固定しておらず、フレキシブルである。そして時とすると、肉体の外部に出てくる。
特別の能力を持った人は、これを自分の意志の力で外部に出すことが出来るという。また病気や疲労などで肉体が消耗しているときには、自然にそれが外に流れ出してしまうこともある。
しかし、外に出ても、生きている限りは、アストラル体は、元の肉体に戻ることが出来る。 アストラル体には、感覚能力・知覚能力・記憶能力なども備わっているので、肉体を離れた状態での体験を思い出すことが出来る。また、アストラル体が離れても、肉体の通常の能力は必ずしも失われないので、肉体は肉体でそのまま日常的な活動を継続することも可能であると言われる。』
一つの解釈・説明として参考にして下さい。
エーテル体とは?
シュタイナーが言う「エーテル体」は、物理学的なエーテル/「光の担い手」ではなく、物質体の至るところに浸透している人間の本質の第二の構成部分を意味します。言うなれば、物質体の一種の「建築家」のように見なす事が出来るとも述べています。
シュタイナーの目には、物質と生命の間に、数字で規定できる違いだけでなく、決定的な相違が映っていたようです。又、シュタイナーは、生命にはその担い手として肉眼には捉えられないエ一テル体(der Aetherleib)が宿っていると考えます。
そのエーテル体が抜け出れば、その生命体は死にます。
そして、シュタイナーは、このエ一テル体を提供する源の世界として、物質界より高次なエ一テル界(die aetherische Welt)を考えていました。
これが生命力の世界です。
人間の場合、エ一テル体は物質体(der physische Leib)に生命を与えているだけでなく形も与え、記憶力やリズム性・習慣性なども担っているとされます。
エ一テル体は超感覚的な観察によると、輪郭は物質体とほぼ同じであるが、内部はリズムをもって流れる流動体と考えています。
芸術的感動や宗教的畏敬の念は、このエ一テル体に良い影響を及ぼすといいます。 シュタイナーは、体とその源であるエ一テル界を構成している素材は、我々が何かを想像する時に浮ぶイメージに、生命を吹き込んだようなものとも考えました。それが前述の ”物質体の一種の「建築家」のように見なす事が出来る” という事に繋がります。
それでは、「自我」とは何ぞや? ・・・・
自然科学、哲学、精神科学、シュタイナーの叙述等々其々の分野で一冊の本になる位に深く興味のあることですので、楽しみながら自分なりの「自我論」を探り出して下さい。
参考までに、フロイトの「精神構造論」では、自我は三層構造になっているとし、下部の自我〜超自我と呼ばれる上部の自我に分類し、快楽原則を原理とし自己を本能的行動に走らせる自我から理性や理想・倫理観のもとに導こうとする超自我と段階的に分け、一体としています。
尚、ルドルフ・シュタイナーが述べている「自我」については、「神秘学概論」の第二章「人間の本質」・第三章「眠りと死」等で述べていますので、そちらを参照下さい。
”自我” ・・・・ 人間の永遠の探求テーマかもしれません。一つの自我論を参考に下記に記載いたします。
≪参考≫”怒り”から導く方法で、「自我」を 「 デカルト的 」 に考察してみました。
医学的には、理性は脳の表面を被っている大脳新皮質の働きによるが、本能や欲望、怒りや恐怖等の情動は、大脳新皮質の下にある大脳辺縁系の働きであり、人間は、理性と情動を連動させることが出来る珍しい動物であるらしい。
この脳の前部・前頭葉(前頭連合野)が巨大化し「自我」という機能を有するようになり自己同一性が保持された。 その結果「死」の恐怖も生まれ、それらの恐怖から免れる方法として『
体が滅んでも、精神(魂)は不滅である 』という考え方が生まれ、宗教などの根本思想となった。
そして、人間が発明した極めて優秀な「心の安定装置」でもあると考えるようにもなる。 この「心の安定装置」/ 宗教での「怒り」の捉え方は、正常な判断力を弱め、自我の弱体にも繋がるので、人間の低次な感情表現と考え、キリスト教では、七つの大罪の一つとしています。
仏教でも、怒りを克服しない人間は「地獄界の精神状態へ導く」と考え、死後最も悪い状態に魂が行く事になるとしています。
生物学的には、「不安」・「いらいら」・「怒り」は、生理的な現象も含めて「 本能的欲求やテリトリーへの侵入に対して、思うがままにならないこと / ストレスや威嚇 」の表現で、 人間の場合には、心と身体の「安定とバランス」が崩れた時の「悲鳴」のようにも感じてしまいます。
≪補足≫
”怒りや死の恐怖”を取り除けたら、どんなに素晴らしいことかと思っていましたが! 1940〜50年代に、脳の前部に有るとされる怒りや恐怖、精神分裂・躁鬱病等の原因を脳全体から分離させ、消去する研究が行われている。
この研究(ロボトミー研究)で、ポルトガル人医師/エガス・モニスは、ノーベル賞まで取っているが、ロボトミー施術で不安や凶暴性、怒りや恐怖(死の恐怖)、喜びや悲しみ等の情動は希薄になるが、人間としての自我(精神)の喪失が問題しされ、
今でもこの分野の研究は、大きなうねりにはなってはいない。
以前に本で読みましたが、アメリカだかカナダの建設作業員が、事故で頭の前部(前頭連合野)に鉄筋を突き刺し、一命は取りとめたが、理性の利かない全く別の人格(”私が私”で無くなってしまう。)になってしまったという話があります。
このことで解かることは、”怒りや恐怖”等の情動は「自我(私は私!)」と連動しているということになり、取り除くと”私”ではなくなってしまうということにもなりますので、「心の安定装置」などの力を借りて共存するしかないみたいです。
又、角度は異なりますが、精神医学者の河合隼雄氏が自我の確立について、下記のように述べています。
自我の確立を西洋流に考える事は、「男性の目」によるものである。「女性の目」を通して見るという場合、自我の在り方からして異なってくるはずである。
そして、この事は必然的に東洋と西洋の対比の問題にまで及んでくるのである。
ノイマンの提出した、西洋近代の自我は----男女を問わず----男性の英雄像で表される。
という説に対して、筆者は、日本人の自我は----男女を問わず----女性像で表されるのではないかという仮説を既に提出した。
|
|
■ |
人間の進化
ダーウィニズムの偉大さを否認することはありません。しかしダーウィニズムは、人間の内的な進化を解明していません。
それはもっぱら、関連性のうちの、顕在的なものしか見ていません。そのため、それは、人間の霊的本質をないがしろにするようなあらゆる純物質的な解明法と全く同じような性質をもつのです。
こうして専ら物理的な事実に基づいた進化論は,人間の起源を動物に求めるのです。
それは彼らが、化石人類において、発達の遅れた低い額を確認したからです。
これに対し、物質的な人間をエーテル的人間の単なる表われと見なす秘教は、ことを全く異なる観点から見ます。
事実,人間のエーテル体は、物質的な体とほとんど同じ形をしており、その輪郭から安々とはみ出ることができます。
|
|
|
《参考》 宇宙(人間)の進化 / 自然科学とは異なる角度で説いています。
シュタイナーは宇宙の進化を、土星期からヴァルカーン期までの惑星状態に分け、その各惑星状態は、七つの生命状態を通過し、各生命状態は七つの形態状態を通過して進化すると考えました。
現在は、第四惑星状態「地球期」の第四生命状態/第四形態状態「アトランティス期」/ゲルマン・アングルサクソン文化期になります。詳しくは「神秘学概論/宇宙進化論」をお読み下さい。
《 参考 - 七つの惑星期 》
1土星期 熱体期/物質体基礎期
2太陽期 エーテル体基礎期
3月期 アストラル体基礎期
4地球期 物質体・エーテル体・アストラル体・自我期
5木星期 自己意識/形象意識期
6金星期 インスピラツィオーン期
7ヴァルカーン期 イントゥイツィオーン期
|
|
■ |
人間について ・・・・・
※物質として外から直視できる人間全体は、【ルツィフェル】の影響の結果なのです。
※物質とは霊(破壊された)の瓦礫の山のことです。
※霊が肉体を凌駕しているエーテル体の中に飛び散る時に神経物質が生じ、三つの素材を見出す。
第一に外界に存在する通常の素材。
第二が植物の中に見られる素材。
第三に不規則になった人体、動物体の中に見られる素材である。
※人間(人体)の将来について
〜聴覚が死滅し、喉頭部が未来の生殖器官となる。
≪註≫この項は、多岐にわたりますので、前後を切り取り要点だけを明記しています。 |
|
■ | 死後・人の眠り
人間が眠りの間に体験する状態を観察する事なしには、目覚めている意識の本質を洞察する事は出来ない。 死を考察する事なしには、生のなぞには迫る事は出来ない。 |
| ≪死後≫
死後すぐ後に来る諸体験は、ひとつの点で生きている間の諸体験とは、全く異なるものである。浄化の間・人間はいわば逆戻りして生きる事になる。人間は誕生して以来、生きているときに体験した全ての事柄をもう一度体験する。
死の直ぐ前の出来事から始まり、誕生までの全てがもう一度逆に体験される。 そして、その際、生前に自我の霊的本性に由来しないすべての出来事が、霊的に眼前に現れる。ただ、人間は、この全ての出来事も逆の仕方で体験する。
例えばある人が、60歳で死に40歳の時に激しい怒りから誰かに肉体的あるいは精神的に苦痛を与えたとすると、その人は死後、生前の生涯を逆に戻って、40歳のところへ達した時、この出来事をもう一度体験するであろう。
ただ、その時は、生前、他者を攻撃する事で生じた充足を体験するのではなく、その代わりに、自分が他者に与えた苦痛を体験するのである。
この浄化の時は、生きてきた間の約1/3を要する。
≪眠り≫
人間が眠りに落ちると、人間の構成部分の関係に変化が生じる。眠っている人間の中で、その場所に横になって居るのは、物質体とエーテル体であって、アストラル体と自我は含まれない。眠っている時にエーテル体は物質体と結合した状態であるので、生命の働きは継続する。
なぜなら、物質体はそれだけで放っておかれるならば、その瞬間に崩壊する事になるなるからである。 しかし眠っている間に消えているものは、さまざまな表象であり、苦悩と快楽や喜びと悲しみであり、意識的な意志を言い表す能力であり、生活に見られる似たような諸事実である。
だが、それらについては、アストラル体が担い手である。 眠りの間に、アストラル体があらゆる快楽と苦悩、全ての表象世界や意志の世界と共に消滅していると言う考えは、とらわれのない判断にとっては、言うまでもなく、全く問題にならない。アストラル体は、まさに別の状態で存在しているのである。
人間の自我とアストラル体は、快楽や苦悩そして先に述べたあらゆる他のものに満たされているだけではなく、それらについての意識的な知覚も持っているが、そのことが意識されるたみめには、アストラル体が、物質体、エーテル体と結びつく事が不可欠である。
目覚めている間はアストラル体は、物質体とエーテル体と結びついているが、眠りの間はそうではない。アストラル体が物質体、エーテル体と結びついているときとは異なる存在のあり方をしているのである。
ここで、アストラル体のこの異なる存在のあり方を考察する事が、超感覚的なものへの認識の課題となる。
|
|
|
■ |
輪廻
人間が物質界の人生で獲得した果実が、霊の国で成就すると、その度に 繰り返し人間は地球上に戻ってくる。 しかし、初めと終わりのない繰り返しは存在しない。人間は、かって、別の存在形式から、既に述べたあり方で経過する存在形式に移ったのであり、未来においては別の存在形式に移行するであろう。
どの人間も、自分の霊的な基本形態に従って、生まれる前に存在している。
なぜなら、霊的に考察すれば、どんな個人も他の個人とは同じではないからである。
それは、ちょうど動物の種が、他の動物の種と同じではないのと同様である。・・・・・・・ 略
略 ・・・・・・・ 霊的探求が述べている、地上生活と地上生活との間の霊的領域の諸事実と関連している繰り返される地上生活(輪廻転生)のみが、このことが、現在の人間の生をあらゆる方面から考察した時に、満足のいく説明をする事が出来るのである。
≪死・再生・カルマ・誕生(輪廻)の考え方≫
人間は、いつまでも自我・アストラル体・エーテル体・物質体の四重の存在でいるわけではない。
いずれ物質体の崩壊による死が訪れる。すると人間は,自我・アストラル体・エーテル体の三重の構成となって、物質界から抜け出る。
この死後の世界で「自我」が意識を維持しながら数日を過した後、エーテル体の分離が起こる。 そして、自我とアストラル体という二重の構成になった人間は、アストラル界に出て、そこで地上の人生のおよそ1/3に相当する期間を過ごす。
その後、アストラル体の分離が起こり、人間は感情にわずらわされない純粋な霊(Geist)となって、「高次の霊的世界」で過ごすことになる。これはふつう数百年かかる。
その数百年のある時期に、「次の生」をどのような体で、「どのような環境」のもとで過ごすのが「霊的進化のために」最も良いかが決まる時がある。
所謂、 「カルマの現れ(Die Offenbarungen des Karma)」です。
そして時が満ち、再び物質界へ向けての下降が始まる。途中アストラル界でアストラル体を、エーテル界でエーテル体を、新たに身につけ、その後母胎に宿って物質体を得た後に、前生を忘れた新しい人生が始まる。
・・・・・・・・ 新たな「誕生」です。 |
|
| |
| |
≪参考≫
ウパニシャッド/ヴェーダ
ヴェーダでは、死後の事を「今の身体を去った後に、直ちにその人の知識と業と前世に関する記憶を伴って、微細な原理である心が執着しているところに赴き、その業の報いを得て、また再びかの世からこの世に行為をなす為に帰ってくる。」と述べています。
この繰り返しの後、欲望を捨て去った者は「心の臓に宿っている欲望が全て捨て去られると、死すべきものは(人間)は不死となり、この世でブラウマンに到達する。」
第一位(普遍位=目覚めの「覚醒状態」)
第二位(光明位=夢見の「夢眠状態」)
第三位(智慧位=欲望も夢も感知しない「熟睡状態」)
第四位(言語表現を超越したアートマン/梵我一如)
又、ウパニシャッドの一体観念は、魂と宇宙の普遍的な原理として、物理主義/合理主義を排したアメリカの超越主義思想の指導的思想家「ラルフ・ワルド・エマーソン【Ralph Waldo Emerson】-(1803年〜1882年)」 などにも影響を与えています。
インドのウパニシャッドに興味のある方は、前田專学氏の「インド哲学へのいざない(ヴェーダとウパニシャッド)」や中村元氏の「ウパニシャッドの思想」等に詳しく書かれています。
| ------------------------- |
≪註≫
Rudolf Steiner
インド人の叡智の書(ヴェーダ)に含まれている内容は、極めて古い時代に、偉大な教師達によって育まれた高次の叡智の本来の姿を伝えているのではなく、そのかすかな余韻を伝えているに過ぎない。
|
|
■ |
人生1
人生は、人間の自我が事実に基づいた態度をとるための偉大な教師である。 |
|
■ |
人生2
人生は、「自我」の内部に物質的な器官そのものの本質に由来するものではないが、物質的な器官によって充足する事のない享楽を求める欲求を燃え上がらせた。 |
|
■ |
人生3
青年時代は”肉体”の季節、中年は”心と知性”の季節、老年は”魂”の季節。
|
|
■ |
感情1
内面にかなり苦しい感情を呼び起こすようなことが、ある人の身に起きたとする。
その人はそれに対して二通りの態度を取る事が出来る。その出来事を苦しい思いをするものとして体験し、苦しい感覚に没頭し、それどころか、ことによると苦しみの中に沈んでしまう可能性もある。
しかし、別の態度を取る事も出来る。実際、私自身が前の人生で私の内部に私をこの出来事に遭わせる力を形成したのだ。私が自ら、私にこのような苦しみを与えたのだ。と言うことが出来る態度である。
そして、このような人は、更にそうした考えをもたらすあらゆる感情を、自分の内部に呼び起こす事が出来る。当然の事であるが、感覚や感情の活動がその様な状態になるためには、そうした考えをこの上なく真剣に、ありとあらゆる力で体験する必要がある。 |
|
■ |
感情2
欠陥を避難する事によって学ぶのではなく、欠陥を理解する事によってのみ学ぶ事が出来る。
しかし、理解する為に不満をすっかり排除しようとするならば、やはり進歩はないであろう。
・・・・ ここで重要なのは一面性ではなく、魂の諸力の安定とバランスなのである。 |
|
■ |
病(やまい)
精神科学は、病気の大部分が、アストラル体における倒錯や錯誤がエーテル体に伝わり、エーテル体を通して、物質体の調和そのものを破壊することに因るものであるという事実を明らかにしている。 |
|
■ |
Doppelganger / ドッペルゲンガー : 境界の守護者
□人間が霊的知覚器官を獲得するところまで規則正しい修練を行うならば、自分自身の姿が最初の印象として自分の前に現れる。
”自分のドッペルゲンガーを知覚するのである。” -----略----- ドッペルゲンガーは「魂的-霊的世界の前に存在する”境界の守護者”」と呼ぶ事ができる。
□人間が「境界の守護者」との出会いなしに霊的−魂的世界に入っていくならば、次々と錯覚に陥るだろう。なぜなら、自分がその世界に持ち込んだものと、その世界に本当に属しているものとを区別することが出来なくなるからである。
□超感覚的世界に入っていく時以外に、人間が、この「境界の守護者」に出会うのは、物質的な死を通過するときである。
≪かなり省略して記載していますので興味のある方は「高次の諸世界の認識」をお読み下さい。≫
※
精神科学或いは霊科学では、生命を物質の延長として捉えず、その存在を、物質界とは別に見ています。
シュタイナーは、「いかにして高次世界の認識を獲得するか」で以下のようにも述べています。「正しい霊的修練を積めば、誰もが物質界とは存在のレベルを異にした生命の世界を、知ることができる。」
その、正しい霊的修練を行うと、自らの「境界の守護者」との出会いがあり、その守護者から「霊的−魂的世界」への正しい導入案内がされるようです。
≪参考≫
ドッペルゲンガー現象 (独: Doppelganger・英: double)/ 自己像幻視現象(オートスコピー)
自分と同じ姿を鏡ではなく、他者として見える現象で、精神病的幻覚にこのような事がある事も知られている。現代医学では、脳の一部(精神)の異常状態で起こる現象とみている。
又、”臨死体験”現象で、体外離脱して上から自分を見ている姿が、類似するものの一つでもあるようで、この現象には非常に興味があります。
”境界の守護者”とは、もう一人の自分 !?
シュタイナーは、そうは叙述していませんが、私には、神秘学的にこの状態(現世)で見る自己像は、肉体(物質体)から遊離した「アストラル体」ではないかと思えてならない?
この現象は、昔から伝説や民話によく出てくる、対面から顔を隠した人がやってきて、すれ違いざまに顔を確認すると、なんと自分の顔だった、という類の話です。日本では芥川龍之介の小説があり、欧米でもこれをテーマにした文学作品はかなり多い。
その他にシューベルトの「白鳥の歌」の中の「ドッペルゲンガー」(ハイネ詩)はこの現象を歌い、ゲーテは「詩と真実」で、失恋時の傷心状態でのドッペルゲンガー体験を述べている。
|
|
■ |
Luzi-fer & Ahriman
ルツィファー / ルツィフェル(Luzi-fer)
人間の内にあらゆる熱狂的な興奮や誤った神秘主義的傾向を呼び起こし、人間を舞い上らせようとしたり、人間の血を生理学的に沸き立たせ、無我夢中にさせようとしたりするものすべてに働いている力の事である。
アーリマン(Ahriman)
人間を味気なく散文的かつ通俗的な者にし、血肉を失わしめ、唯物主義の迷信に導く力の事である。 |
|
■ |
忘却
「自我」にとっての記憶と忘却は、アストラル体にとっての目覚めと眠りによく似ている。眠りが昼間の心配や憂いを無のなかに消し去るように、忘却は、人生の嫌な経験の上にヴェールをかけ、それによって、過去の一部を消してしまう。
そして、消耗した生命力が新たに強められる為には、眠りが必要であるように、人間は、新しい体験に自由にとらわれなく向かい合うつもりならば、記憶から自分の過去のある部分を消し去らなければならない。
しかし、まさに忘却から、新しいものを知覚する力が呼び覚まされるのである。 |
|
■ |
判断
"私"の内部には、現在"私"が持っている判断能力よりも正しく"私"を導いてくれる何かが存在している。
"私"はこの「"私"の内部の何か」に対して、"私"の感覚を開いておかなければならない。
そこまでは"私"の判断能力はまだ成就していないのだ、と。魂が人生のそのような場合に注意をを向けていれば、その何かは、魂にとっても有効に働きかける。
そのとき、時々の人間の判断力で見通せる以上のものが、人間の内部には存在しているのだという事が、健全な予感のように、魂にあきらかとなる。このような注意深さは、魂の活動が拡張するように働く。
しかしこの場合にも容易ならぬ一面性が生じる可能性がある。"予感"が自分をあれこれの事柄に駆り立てるので、常に自分の判断を排除する習慣をつけようとする者は、あらゆる不確かな衝動に翻弄されるであろう。
そして、そのように習慣となった判断しない状態と迷信との間には、大きな違いは無いのである。 |
|
■ |
努力
自分の努力の全ては、常に 語らねばならぬこと、又、なすべきだと信じる事を、個人的観点 からではなく、具体化する事にある。
様々な領域で 人格的なものが人間の活動に最も重要な色合いを 与えると言うのが、自分の考えであるが、この人格的なものとは、自分自身の人格性を考慮する事によってではなく、人が語り、行為する仕方によって現れるに違いないと信じている。
よって、自分自身が努力でしなければならない事柄が明らかになる。 |
|
■ |
善意
心からの善意とは、ある魂が他の魂の関心事をいわば吸収し、自分の関心事にしてしまう事によって生じるのだ、と魂は考える事が出来る。そして、魂は、心からの善意というこのような道徳的な理念に喜びを感じることができるようになる。
それは、感覚世界の個々の出来事に対する喜びではなく、理念そのものに対する喜びなのである。その様な喜びを、暫らくの間、魂の中で生き生きとした状態にさせようと試みるならば、それが感情への沈潜である。 |
|
■ |
善と悪
かつて人間の内に動物性が混在していたように、現在、善と悪、あるいは、真と偽りという、相対立する二つのものが混在しています。この対立矛盾、すなわち、二つの要素がみずからの内で混在する仕方によって人間のカルマ、運命が形造られています。
いつの日か人間は、悪を客体として捨て去ることでしょう。こうした事柄を我々はすべて黙示録的な記述のうちに見出すのです。
|
|
■ |
マニ教の善と悪
マニ教の教義の核心は、善と悪の命題です。ふつうの見方では、善と悪とはお互い結びつきをもたず、絶対的な対立を成して、相矛盾するものです。
しかし、マニ教徒の考えでは、悪は宇宙の構成に欠かせぬ要素です。悪は宇宙の進化に参与します。 そして結局は善によって吸収され変化させられます。この世における善と悪、楽と苦の意義を究めることが、マニ教徒の大きな、唯一の使命なのです。 |
|
■ |
危機と理念の上昇
人間が現代ほど大変な危機に瀕していた時はいまだかつてなかったのです。万人の主であるものは、万人のしもべたるべきです。このことは、大いなる必然として生じねばなりません。
真のモラルは偉大な宇宙法則の認識から生まれるのです。偉大な理念は、我々の理想を徐々に前進せしめる活力の源泉なのです。我々は人生のうちの静かな瞬間に、偉大な進化の理念と相まみえるところまで上昇すべきです。 |
|
■ |
表象の背後へ
眼に見える世界の背後には、眼に見えない世界、すなわち 感覚とこの感覚に縛られた思考にとっては隠されている世界が存在するということと、人間の内部にまどろんでいる能力を発展させる事によりこの隠されている世界に立ち入る事が人間には可能であるということ。 |
|
■ |
芸術
真の芸術による影響は、人間に作用する。人間が芸術作品の外的な形、色彩、音を通して、その作品の霊的基盤に表象と感情を浸透させると、それによって自我が受けとる衝動は、実際にエーテル体にまで作用する。
この考え方を最後まで進めていくならば、芸術が、人類のあらゆる進化にとって、どんなに大きな意味を持っているかが正しく判断できるであろう。 |
|
■ |
理想
人生の中で理想が演じる役割は、機械の中で演じる蒸気の役割なのです。 |
|
■ |
動植物
植物に意識があり、動物に記憶があると考える誤り。 |
|
■ |
民話や伝記
諸民族の民話や伝記の宝庫は、元来、霊的体験から生まれたのである。 なぜなら多くの人々のおぼろげな透視能力は、現代からそれほど離れていない過去の時代まで続いていたからである。
確かに、透視能力を失ってはいるが、感覚的-物質的世界に対して身に着けたさまざまな能力を、透視能力に対応する感情や感覚に従って、十分に発達させた人々もいた。 |
|
■ |
オイリュトミー
人間は、現在あるそのままの姿として完成した形をしている。しかし、この完成した形は、運動によって生み出されているのである。
そして、私達は、その中で 「オイリュトミー」を作り出す根源運動の中へ遡っていく。・・・ まさに、見える歌なのである。
マリー・シュタイナー
オイリュトミーすると言う事は、動作によって歌う事です。それは歌であって、舞踏でも、芝居でもないのです。まさに歌う事なのです。 |